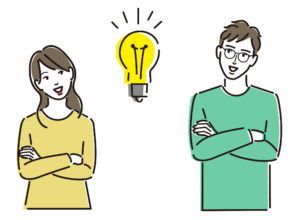昭和99年 ニッポン反転(2)

電機メーカーの設計者としてバブル期を過ごしてきた自分から見ても、中央研究所は確かに事業に結びつきそうにない研究開発もあったと思う。
一方で短期的な視点に捉われない研究によって、そこから他社に追従を許さないようなヒット商品となった技術もあったことは事実。
当時、企業が各自の研究所で”費用”と”技術”を抱えていたことを、今は”ベンチャーキャピタル”と”スタートアップ”が担っているという状況なのだろう。
そうであれば、日本の官民としてももう一度、制度的にも資金的にもしっかり取り組んでいかないと「科学技術立国ニッポン」の復活はあり得ず、自分としてもここに貢献していきたいと考えている。
米国はテクノロジーを目利きできる国の専門家が、主に大学の若手研究者に的を絞り、商業化までを支援した。
1999年 中小企業技術革新制度
研究者支援、本質とズレ
(日経新聞 2024/1/4 朝刊記事)
バブル経済崩壊後の1990年代、経営が悪化した日本企業は中央研究所を相次ぎ閉じ、基礎研究を縮小した。イノベーションの担い手が勢いを失うなか、新たな先導役として期待されたのが大学だった。
政府は1999年、大学の研究成果の実用化を後押しする「中小企業技術革新制度」を整えた。米国が70年代の不況の反省を受け、研究者の起業を支援するために82年に創設した「SBIR(スモール・ビジネス・イノベーション開発法)制度」に倣った。
米国はテクノロジーを目利きできる国の専門家が、主に大学の若手研究者に的を絞り、商業化までを支援した。基礎研究は実用化まで時間を要し、民間は投資をためらう。このリスクを国が背負い、テクノロジー大国復活の道を開いた。
一方で日本は既存の中小企業向け補助金の看板をすげ替えたケースが多かった。実績のない若い研究者は支援を受けにくく、大学の科学研究を実用化する効果は乏しかった。研究者支援の制度の本質をはき違え、大学を革新の源泉に転換するのに失敗した。
研究力を高める投資も細る。大学の人件費などに充てる運営費交付金は、23年度が1兆784億円と04年度比で13%減った。
経費削減でポストが減ると、研究者を志す若者も少なくなった。文部科学省によると20年度の日本の博士号取得者は1万5564人で、00年度から3%減った。米国は19年度までに2.4倍に増えた。
国公立大学を再編し、人材や資金を戦略分野に集中するような抜本的な改革も求められる。